こんにちは。Mackerel CREチームテクニカルサポートの ![]() id:masarasi です。
id:masarasi です。
8月7日(木)に、株式会社さくらインターネット、株式会社X-Tech5、株式会社はてなの3社共催イベント「国産サービスで実践するオブザーバビリティ入門」を開催しました!
この記事では当日の様子のご紹介や、セッションやパネルディスカッションを参加者として拝聴した感想を交えたレポートをお届けします。ここでご紹介するのはイベントのほんの一部なので、興味を持たれた方はぜひアーカイブをご視聴ください。
- 💁 イベント内容
- 🎬 配信アーカイブ
- 🎤 セッションパート
- 💬 コメントで振り返る:「どこから始める?」「なぜ国産?」──パネルディスカッション
- 📝 参加者や登壇者の方々によるイベントの感想
- 🐟 ご参加ありがとうございました!

💁 イベント内容
🎬 配信アーカイブ
🎤 セッションパート
前半は登壇者3名によるセッションパートでした。各セッションの概要を ![]() id:masarasi 個人の感想とともにお届けします。
id:masarasi 個人の感想とともにお届けします。
「国産サービスで実践するオブザーバビリティ入門」を執筆して感じた国産ツールの魅力

本イベントのタイトルにもある「国産サービスで実践するオブザーバビリティ入門」。その著者の一人である、株式会社X-Tech5 菊池 宣明さまによるセッションでは、国産、海外産のサービスが数多く存在する中で国産サービスを選ぶ理由や、国産サービスならではの魅力について語っていただきました。
配信アーカイブの該当部分は 5:34 からです。
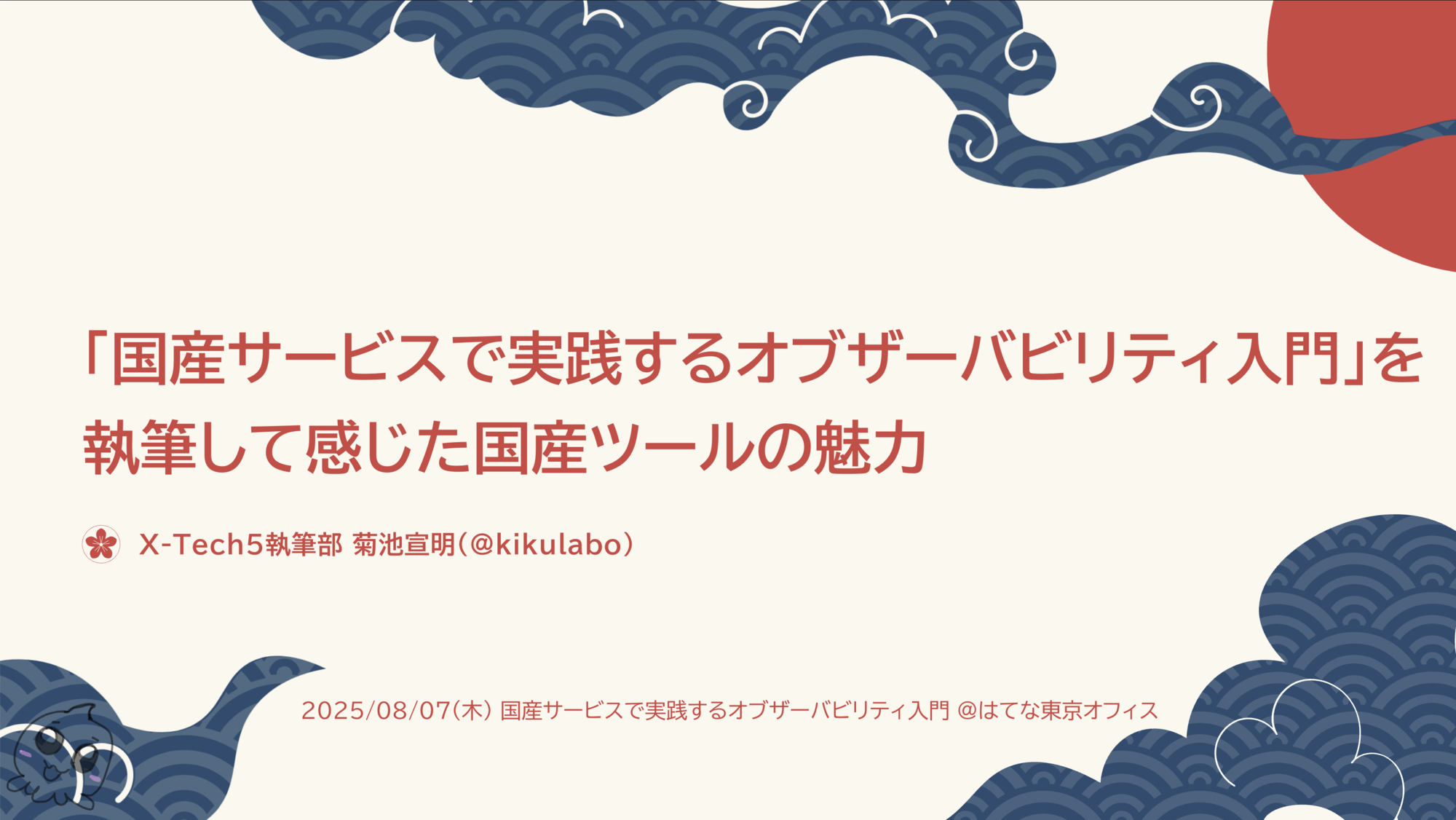
感想
国産サービスには言語の壁がなく、UI上の日本語が自然であったり、サポートを日本語で受けられたりするので安心して利用できる、というのはうれしいポイントですよね。また、今回のイベントのように開発者に会ってフィードバックがしやすいというのも国産ならではだと想います。「国産サービスを盛り上げたいという思いを込めて、国産サービスで実践するオブザーバビリティ入門を執筆した」というお話が印象的でした。
𝕏の実況ポスト
翻訳の難しさあるよね。
— そーだい@初代ALF (@soudai1025) 2025年8月7日
例えばAWSで、インスタンスの終了と停止があって終了するとインスタンス消えるやつな。 #国産サービスでo11y
「中小規模チームや学習にも『ちょうどいい』ボリューム」が魅力のひとつ #国産サービスでo11y
— yasunori (@yasunori_k_) 2025年8月7日
中央集権的にじゃなくて、みんなが使えるツールってところ大事だな。。。
— こうじゅん@SRE (@kouzyunJa) 2025年8月7日
#国産サービスでo11y
Mackerel in さくらのクラウド

さくらインターネット株式会社 久保 達彦さまによるセッションでは、さくらのクラウドでMackerelがどのように利用されているかや、さくらインターネット社におけるオブザーバビリティの取り組みについて紹介していただきました。
配信アーカイブの該当部分は 21:30 からです。
感想
さくらインターネットさまでは、ユーザー登録をMackerelのSAML認証機能で自動化したり、Githubやterraformを連携して設定のIaC化をしたりしていて、Mackerelを交えた実際の運用のお話を聞くことができました。また、今後のMackerelへの要望とその要望の背景についてもお話しいただき、このような深いお話が聞けるのはイベントならではだなと感じましたし、ユーザーのみなさまがMackerelをもっと便利に使ってもらえるように、我々CREもがんばりたいなとあらためて思いました。
𝕏の実況ポスト
さくらインターネットではmackerelを使ってます。以前はSREの部署がオーナーシップを持っていたが環境を整え、他チームでの事例も増えてきた #国産サービスでo11y
— Masahiro Nagano / 長野雅広 (@kazeburo) 2025年8月7日
https://t.co/btrjJP8Ufm
— Masahiro Nagano / 長野雅広 (@kazeburo) 2025年8月7日
さくらのクラウド向けのotel collector公開してます
#国産サービスでo11y
IP アドレス一覧を JSON で配布してくれ、みたいな要望を投げていただけるの、いつもありがとうございます。 (こんなユースケースの分かりやすい要望は本当に助かる) #国産サービスでo11y
— Takafumi ONAKA (@onk) 2025年8月7日
オブザーバビリティ文化を組織に浸透させるには

弊社、株式会社はてなの大仲 能史によるセッションは、はてなやMackerelチーム内でのオブザーバビリティの取り組みや、オブザーバビリティを組織に浸透させるためのコツについて語った内容になっています。
配信アーカイブの該当部分は 34:44 からです。
感想
サービスが動くインフラやそのリソースの監視はインフラチームやSREの仕事になりがちですが、アプリケーションの監視(APM)となると、開発者も巻き込んでいく必要がありますよね。時にはそれがネックになって、オブザーバビリティには興味があるけどなかなか進められない、というケースがあるかもしれません。そういう方にこそ(そうでない方にも)見て欲しい、オブザーバビリティを組織に浸透させるための工夫やコツがたくさん詰まった内容になっています。
𝕏の実況ポスト
「チームみんなで育てる監視」
— こたつ&&みかん (@kota2and3kan) 2025年8月7日
このフレーズ、とても良い。#国産サービスでo11y
「SLOを割っていないのに障害対応していたらSLO設定が足りてないんじゃないっていう発想」なるほど
— こうじゅん@SRE (@kouzyunJa) 2025年8月7日
#国産サービスでo11y
オブザーバビリティが足りなければ計装を追加する、さすがだ。良い文化 #国産サービスでo11y
— きくち (@kikulabo) 2025年8月7日
💬 コメントで振り返る:「どこから始める?」「なぜ国産?」──パネルディスカッション

後半はセッションの登壇者3名に加えて、株式会社X-Tech5 馬場 俊彰さま、さくらインターネット株式会社 長野 雅広さまを迎え、モデレーターはMackerelエヴァンジェリストの曽根 壮大さまという布陣でパネルディスカッションが行われました。トークテーマは以下の内容になっています。いくつかのテーマはイベント参加者からslidoへ投稿されたご質問になっています。
- オブザーバビリティは本当に"高い"のか?その裏にある課題とは?
- コストを抑えてオブザーバビリティを始めるために心がけたいこと
- 当事者が語る"国産ならではのよさ"実際のところどうなの?
- 国産ゆえのデメリット
- Mackerelの今後の課題
- AIの発展によるオブザーバビリティへの向き合い方の変化
配信アーカイブの該当部分は 1:02:20 からです。
印象的だったコメントをご紹介します。
🛠️ オブザーバビリティをどこから始めたらいい?
「どれかからだけ始めるんだったら、ロードバランサーのメトリクス。エラーとレイテンシーを見ると、自分の話としてみんな入りやすい」(馬場さま)
最初の一歩として、自分の手元に近いところを観測するのは実感しやすく、納得感があります。
「デベロッパーの人が一番感動するのはトレース。トレースを一回突っ込んでみて。『本番で見れるんだ』『どこが悪いか分かるから、簡単に直せる』ってなって感動する」(馬場さま)
トレースの“可視化されている”感覚は、実際に動かして初めて腹落ちすることが多いですね。導入のきっかけとしても効果的だと感じました。
𝕏の実況ポスト
外側のメトリクスから見ていくのは確かにそうだなぁ。基本はGrafanaでCloudWatchメトリクス見るくらいで10年くらいやってきてた。 #国産サービスでo11y
— Hayato OKUMOTO (@falcon_8823) 2025年8月7日
🤝 国産サービスの強みとは?
「外資だと話せるのはサポートの人。国産だと、偉い人(意思決定層)や開発者と直接話せる」(馬場さま)
エンジニアとして細かな改善要望を直接伝えられるのは、現場視点からもありがたいポイントです。
「“なぜ・なに”の会話ができる。例えば『小さいインスタンスがほしい』の背景に『起動が遅い』ことが課題かもしれない、と具体的な話ができる」(長野さま)
表面的な要望ではなく、背景や本質まで一緒に掘り下げられる。この距離感は国産サービスならではですね。
𝕏の実況ポスト
直接話ができると話が早いのはありますよね。顔見知りだといきなりPR送りつけても通りやすい… #国産サービスでo11y
— fujiwara (@fujiwara) 2025年8月7日
「この画面イラっとした」ぐらいのものでも問い合わせ (改善要望) を投げて良いらしいwww#国産サービスでo11y
— こたつ&&みかん (@kota2and3kan) 2025年8月7日
言語の壁でWhyを伝えづらい、わかるなぁ... #国産サービスでo11y
— tak_0x00 (@tak_0x00) 2025年8月7日
💡 国産だからこその課題と、それでも挑む理由
「外資系と比べて開発体力や機能で見劣りする部分もある。でもそこに甘えないで、機能を絞ってでも出していくなど、日本のサービスとしてちゃんと向き合っていく」(長野さま)
リソースに制限があっても、真摯にユーザーと向き合う姿勢は、プロダクトにじわじわと反映されていくと思います。
「国産の技術を残したい。なくなったら、未来永劫、作れなくなる。国のために、何かあった際のリスクのためにそういった作れる技術を残していく必要がある」(長野さま)
こうした思想が背景にあるからこそ、自分たちも国産ツールに携わる意義を持って取り組めるのだと再認識しました。
「AIが進んでも、責任を取れるのは人間。エンジニアの仕事はなくならない」(馬場さま)
道具は進化しても、責任と判断は人が担う。だからこそ、エンジニアは今後も求められ続けると感じます。
𝕏の実況ポスト
「『国産』を作れる技術を残していきたい」
— こたつ&&みかん (@kota2and3kan) 2025年8月7日
かっこいい。#国産サービスでo11y
大変面白かった。改めてMackerelが目指すものだったり、オブザーバビリティが当たり前になりつつ現在とAIの未来の役割について、方向性が確立できたと思う。国産も応援していきたい!感動!🙌 #国産サービスでo11y
— adachin👾SRE (@adachin0817) 2025年8月7日
📝 参加者や登壇者の方々によるイベントの感想
参加者や登壇者の方々がイベントについてのブログを投稿してくださっているのでご紹介します。
🐟 ご参加ありがとうございました!
今後もMackerelではイベントを開催予定です。Xやconnpassにて告知いたしますので、ぜひフォローをお願いします。
次回もMackerelのイベントでお会いしましょう!